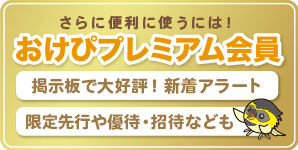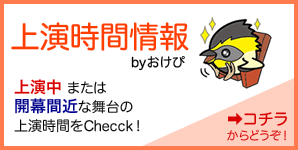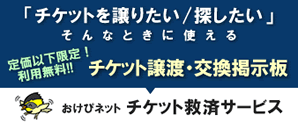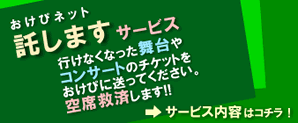- new おけぴ会員マイページができました
掲載日:2023/03/12
【2023年の日本で上演されるということ】ミュージカル『太平洋序曲』開幕直前会見&ゲネプロレポート
スティーヴン・ソンドハイム作曲、ミュージカル『太平洋序曲』が梅田芸術劇場と英国メニエールチョコレートファクトリー劇場による日英合作で新制作。2023年3月、日生劇場にてその幕が上がりました。西洋のクリエイターによって描かれた「幕末の日本」が西洋と日本の融合したアプローチでどう立ち上がるのか。
注目のクリエイター陣は、演出を『TOP HAT』を手掛けたマシュー・ホワイトさんが手掛け、そこに数々のソンドハイム作品を手掛けたウエストエンドを代表する音楽監督のキャサリン・ジェイズさん、美術家ポール・ファーンズワースさんに加え、日本からは衣裳家の前田文子さんが参加し新たな『太平洋序曲』が作り上げます。舞台写真と開幕直前会見のコメントと共にゲネプロの様子をレポートいたします。(狂言回し:山本耕史さん、香山弥左衛門:海宝直人さん、ジョン万次郎:ウエンツ瑛士さん)
劇場に入ると、舞台上に広がる木と曲線が印象的な美しい舞台美術が目に飛び込みます。波やたわわに実った稲穂、月……さまざまなモチーフを映し出す上手後方の円も効果的。
時は江戸末期。ペリーの乗った黒船来航から物語は始まります。
山本耕史さん演じる狂言回し(松下優也さんとのWキャスト)のリードで「The Advantages of Floating in the Middle of the Sea」に乗せて、鎖国政策をとっていた静かなで平和な当時の島国日本の様子が描かれます。それがニッポン! 山本さんの緩急自在の声の求心力、遠くにたたずみ物事を眺めていたかと思ったらすっとその中心に入り込むような存在の濃淡をも自在に操る力量が物語をけん引します。


この曲をお気に入りと挙げたのは香山弥左衛門役Wキャストの廣瀬友祐さん。
「すべて惹きつけられる素晴らしい曲ですが、この物語の1853年の日本というものを紹介する。この世界に入り込む最初の曲なので好きです」
幕府は慌てて、浦賀奉行所の下級武士 香山弥左衛門を交渉にあたらせることに。目付け役への昇格ながら、その仕事はアメリカを追い払うという困難を極めるもの。もし失敗したら……不安を感じながら香山(海宝直人さん)と妻たまて(綿引さやかさん)が歌うのが「There Is No Other Way」。

互いを思い合い静かに暮らしていた香山と妻のたまての身に起きた突然の出来事
「香山とたまてが引き裂かれていく様子。(任務のために)行くしかない香山、見守るたまて、二人の気持ちを察すると……稽古場から涙ぐんで見ていました」こう語るのはジョン万次郎役Wキャスト 立石俊樹さん。ほかに道はない、切羽詰まった状況ながらそのメロディはどこか抑制がきいたもの。受け入れ、静かに覚悟を決める、日本人の情緒を表すような楽曲です。美しい笛の音が切ない。
海宝さんは香山の役作りについて「香山というキャラクターは日本が歩んだ開国までの動乱の時代を象徴している人物。キャラクターが立った登場人物の中でとてもニュートラル、普通の人として描かれている。お客様が感情移入できるキャラクターであるということを大切にしました」と語ります。
そんな海宝さんがお気に入りに挙げたのは「黒船来航で江戸が大騒ぎになる。その最初の混乱を描いたFour Black Dragonsを挙げたいと思います。アメリカの4隻の船を黒い龍に見立てた市民たちの歌です。彼らの言葉、叫びで描かれるスペクタクル性にあふれた素晴らしい楽曲です」

「Four Black Dragons」は歌い出しの漁師(染谷洸太さん)、泥棒(村井成仁さん)の歌声の素晴らしさに思わず聞き惚れてしまいそうになりますが、そこで語られるのは恐怖と混乱。次第に混乱の輪が広がっていくと音楽もスケールアップ。また本作全編を通して、お一人お一人が強い声を持ち、さらには身体表現にも長けている複数役を担うみなさんの力強さが作品を支えます。みなさんがあまりに素晴らしく、曲の難解さを感じさせないほどですが、実際はとても複雑な表現が求められるのですよね。


ここでもう一人の青年ジョン万次郎の登場です。演じるのはウエンツ瑛士さん。
漁に出て遭難、アメリカ人に助けられたジョン万次郎が帰国。日本への帰路で黒い軍艦の存在を目撃した万次郎はその危機を幕府に訴えるも、当時の法により死罪を告げられる。そこに香山のとある発案が届き、万次郎はアメリカとの交渉に同行することで死罪を免れるのです。
浦賀への道中、二人が連歌で交流を深めていく場面に歌われるのが「Poems」。まるで即興で、その場でこぼれ落ちた詩にメロディがついたような歌唱、単語をポンポンと投げかけるそれだけでも言葉を美しく響かせる海宝さん、ウエンツさんの軽やかな表現。

漁師と武士、身分違いの友。
「友よ!」こうして二人の交流が始まるのです。
また役作りについてウエンツさんは「国外へ出ることも、戻ってくることも死罪となる時代に、日本に暮らす人に彼はどう見えていたのか。史実の中の万次郎と、狂言回しの話の中の万次郎、そのバランスが難しかった」と、一方、Wキャストの立石さんは「本作における万次郎の役割を掴むのはすごく時間がかかりました。(性格付けに関しては)史実に基づいた謙虚、エネルギッシュ、人懐っこいところが前面に出るように心掛けました」と誰もが知る実在の人物ゆえの苦労を語りました。
「Poems」をお気に入りに挙げたのはウエンツさん。
「まずは俳句が歌になっていることの衝撃。俳句として成立する美しい歌詞を日本へのリスペクトを感じさせながらもやはり西洋の旋律に乗せるという唯一無二のミュージカルナンバー。もともと英語で書かれたものを俳句に戻しているという仕掛けも面白いです」
この曲を選んだのは、実はウエンツさんのほかにももうお一人、この日ご登壇された本作脚本のジョン・ワイドマンさんです。「シンプルな形の中で、二人の男たちが共に歩んでいく。はじめは共に旅をするのが難しい状態から、最後には一対になるところを美しく描いている」と「Poems」の魅力を語ります。

こうして秘密裏に進められた香山のアメリカ人日本上陸阻止作戦。誰も知る由もないはずの“その日に何が起きたのか”について、かつてそれを木の上から見ていたという老人(武藤寛さん)、少年(幼き日の老人:谷口あかりさん)、床下に潜んでいた男(染谷洸太さん)が語る楽曲が「Someone in a Tree」。それをリードするのはもちろん狂言回し。
ワイドマンさんは、まず「もしここにスティーヴンがいたら、みなさんのお気に入りの曲についてのお話のすべてに『その通りだ』と同意し、感動したでしょう。彼の曲を俳優のみなさんがこんなにも的確に意図を理解して、美しく歌ってくださっていることを嬉しく思います」とご登壇されたキャストのみなさんのお話に賛辞を贈ります。また、「一番お気に入りの作品は」と問われたときは「一つお気に入りがあるわけでなく、それぞれ違う理由で好きだ」と答えていたソンドハイムさんですが、「お気に入りの曲は」と問われると『太平洋序曲』のこの「Someone in a Tree」だと答えていたそうです。
その理由は。
「スティーヴンの頭の中にある知能と感情のパズルを解き明かすように哲学的な問題を解いていく楽曲です。アメリカ人たちが来たときに書簡を渡したけれどなにも解決しなかった。そんな小屋での会談の様子を証言するそれぞれの歌い手の役がうまく音楽で描き出されるのです」


最後にご紹介するのは香山が歌う「A Bowler Hat」。山高帽というタイトルのこの大曲の中で、香山は西洋文化に、逆に万次郎は国粋主義へと傾倒していく。その思想を象徴するのがTeaと茶道、洋服と和装。生活様式に如実に表れるのです。海宝さんの揺るぎない歌声が香山の信念と重なり、どこか狂気じみたものすら感じさせます。正直で真面目な普通の男だった香山が……。
こうして、もと居た価値観から真逆となる二人を待ち受ける運命は。狂言回しが導くこの物語の結末はいかに! また会見で廣瀬さんがおっしゃっていた「3役がWキャスト、日替わりでキャスト(相手役)が変わっていくというのも舞台の醍醐味です。日々、舞台上で対峙することで生まれるやり取りを大切に演じたいと思っています」という言葉。組み合わせによってまた違うものが生まれそうです。
また、インパクトある将軍を演じ切り、一方では若い娘たちにを誘惑術を教える女将を妖艶に演じた朝海ひかるさん、大きな存在感を示す老中の可知寛子さん、かなり潔くステレオタイプで描かれる西洋各国提督たちを演じるみなさんをはじめとするシングルキャストで作品を支えるみなさんの総合力の高さも素晴らしい!
唯一無二の魅力を持つ音楽、緻密でトリッキーな物語展開、日本の静と諸外国の動をパフォーマンスで表現する手法、無駄を省いた美しい美術、照明、衣裳、振付、そして俳優とオーケストラの素晴らしい表現。作品の高い完成度には唸るしかないのですが、この作品が放つメッセージをどう受け止めるかとなると、個人的に、その距離感は思っていた以上に難しいと感じました。
当時の日本や諸外国の描かれ方は虚実入り混じる創作と理解することができますが、1976年にブロードウェイで初演されたこの作品。1976年から見た「幕末の日本」と「その時の日本」(急激な西洋化、敗戦、高度成長期を経てバブル期へと突入する経済・産業において絶好調だった)の対比から、約50年が経過した今の日本でこの作品を観て、なんだかその50年への思いが心の中でざわざわと不協和音を奏でるような感覚です(作品がというより受け止め側の問題として)。
強引に開国を迫り、受け入れさせた過程は決して平和的とは言えない。「太平洋貿易の始まり」と「平和的な交渉」という2つの意味を持つタイトル『太平洋序曲 Pacific Overtures』にこめられた皮肉。それに象徴されるような批評性にあふれた本作。狂言回しの「170年前」という言葉は1853年、1976年、そして2023年を線で結ぶ。時を超えて、また新たな響きを生み出しながら上演が繰り返されていくというのも名作の証なのかもしれません。変わらぬは、歴史の陰には誰かの思惑があり、誰かが糸を引いているということでしょうか。
最後に、本作を観るために来日されたジョン・ワイドマンさんの言葉を紹介いたします。

ジョン・ワイドマンさん(脚本)、廣瀬友祐さん、海宝直人さん、ウエンツ瑛士さん、立石俊樹さん(初日前囲み取材より)
「スティーヴン・ソンドハイムとは3つの作品を作りました。今も世界中でそれぞれの作品が上演されています。その中でも『太平洋序曲』が日本で上演されることは特別なことだと捉えています。
また、今回の上演、2017年に上演したバージョン(に基づく)においてはスティーヴンと演出のジョン・ドイルと私で、今一度作品を精査し、ストーリーに必要なものを抽出しエッセンシャルでないものを取り除きました。それによってお客様がより物語の核心に触れられることを目的として。そのためにカットした歌は「Chrysanthemum Tea」の1曲です。とても人気のある曲でしたが、カットすることで香山と万次郎にフォーカスを当てて物語が前に進んでいくようになりました」
日本で上演されることの特別感、それは日本の観客がどう受け止めるかも含めてのことでしょう。2023年の日本で上演されるミュージカル『太平洋序曲』は、3月29日まで日生劇場にて上演、その後、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて4月8日~16日に上演されます。
ものがたり
時は江戸時代末期。海に浮かぶ島国ニッポン。
黒船に乗ったペリーがアメリカから来航。鎖国政策を敷く幕府は慌て、浦賀奉行所の下級武士、香山弥左衛門(海宝直人・廣瀬友祐)と、鎖国破りの罪で捕らえられたジョン万次郎(ウエンツ瑛士・立石俊樹)を派遣し、上陸を阻止すべく交渉を始める。一度は危機を切り抜けるものの、続いて諸外国の提督が列を成して開国を迫りくる。
目まぐるしく動く時代。狂言回し(山本耕史・松下優也)が見つめる中、日本は開国へと否応なく舵を切るのだった。
【公演情報】
ミュージカル『太平洋序曲』
【東京】2023年3月8日(水)~29日(水)日生劇場
【大阪】2023年4月8日(土)~16日(日)梅田芸術劇場メインホール
<スタッフ>
作詞・作曲 スティーヴン・ソンドハイム
脚本 ジョン・ワイドマン
演出 マシュー・ホワイト
翻訳・訳詞 市川洋二郎
<キャスト>
狂言回し 山本耕史・松下優也(Wキャスト)
香山弥左衛門 海宝直人・廣瀬友祐(Wキャスト)
ジョン万次郎 ウエンツ瑛士・立石俊樹(Wキャスト)
将軍/女将 朝海ひかる
[老中] 可知寛子/ [たまて] 綿引さやか/ [漁師] 染谷洸太/ [泥棒] 村井成仁/ [少年] 谷口あかり/ [提督] 杉浦奎介/
[提督] 武藤寛/ [提督] 田村雄一/ [提督] 中西勝之/ [提督] 照井裕隆/ [水兵] 藤田宏樹/ [少女] 井上花菜 (登場順)
公式HP:https://www.umegei.com/pacific-overtures/
ミュージカル『太平洋序曲』
【東京】2023年3月8日(水)~29日(水)日生劇場
【大阪】2023年4月8日(土)~16日(日)梅田芸術劇場メインホール
<スタッフ>
作詞・作曲 スティーヴン・ソンドハイム
脚本 ジョン・ワイドマン
演出 マシュー・ホワイト
翻訳・訳詞 市川洋二郎
<キャスト>
狂言回し 山本耕史・松下優也(Wキャスト)
香山弥左衛門 海宝直人・廣瀬友祐(Wキャスト)
ジョン万次郎 ウエンツ瑛士・立石俊樹(Wキャスト)
将軍/女将 朝海ひかる
[老中] 可知寛子/ [たまて] 綿引さやか/ [漁師] 染谷洸太/ [泥棒] 村井成仁/ [少年] 谷口あかり/ [提督] 杉浦奎介/
[提督] 武藤寛/ [提督] 田村雄一/ [提督] 中西勝之/ [提督] 照井裕隆/ [水兵] 藤田宏樹/ [少女] 井上花菜 (登場順)
公式HP:https://www.umegei.com/pacific-overtures/
おけぴ取材班:chiaki(撮影・文)監修:おけぴ管理人
ページトップへ