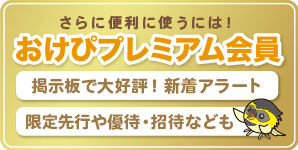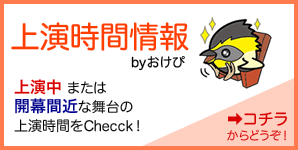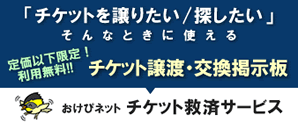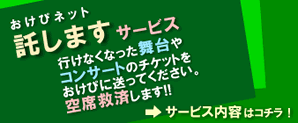- new おけぴ会員マイページができました
掲載日:2024/06/28
世田谷パブリックシアター『饗宴/SYMPOSION』橋本ロマンスさん、白井晃さん対談
7月、気鋭の演出家・振付家の橋本ロマンスさんの演出・振付による新作パフォーマンス公演『饗宴/SYMPOSION』が世田谷パブリックシアターにて上演!

橋本ロマンスさん、白井晃さん
コロナ禍の社会に「ファウスト」「死の舞踏」のイメージを照らした『デビルダンス』
(21年)や、東京に生きる若者の焦燥感を映し出す『Pan』(21年、23年)など、革新的な視点で現代社会をとらえた作品を精力的に発表している橋本ロマンスさん。世田谷パブリックシアター芸術監督の白井晃さんとの対談が実現。
どのような作品なのかとともに、どのような人がどのような環境で、過程で創作しているのか。そのことの重要性にも気づかせてくれるお二人の話。『饗宴/SYMPOSION』がますます楽しみになります。

──まず、白井さんと橋本さんの出会い、そこから世田谷パブリックシアター主催公演として橋本ロマンスさんの新作『饗宴』上演を決定するまでのお話から伺っていきます。
白井:僕がKAAT神奈川芸術劇場の芸術監督をしていたときに『デビルダンス』を拝見し、作品から大きな衝撃を受けるとともに、橋本さんの舞台に対する意識、美学に共感を覚えました。そこで知り合いを通じてお話をする機会を設けていただきました。最初は仕事云々ではなく、お話しただけでしたが、ぜひお仕事でご一緒したいと思うようになり、僕が構成・演出をした高橋一生さんの一人芝居『2020(ニーゼロニーゼロ)』(パルコ・プロデュース2022)に参加していただきました。そして、世田谷パブリックシアターの芸術監督になり、僕自身が主体的にラインアップを決めるようになった最初の年度である2024年度に、プログラムのひとつを橋本さんに手掛けていただきたいと思いお声がけしました。
──ラインアップ説明会でも、白井さんがこれから打ち出していく方向性、劇場の在り方を象徴する演目だと感じました。それを受けて、橋本さんはどう感じましたか。
橋本:すぐに、「やります」と答えました。ただ、正直に言うと、お話をいただいたときは主劇場(世田谷パブリックシアター)だとは予想していませんでした。白井さんから、この劇場をフィジカルシアターなど様々な形態のパフォーマンスを上演する場所にしていきたいということ、若いアーティストの創作する場となってほしいという思いから、私が主劇場の演出を手掛けることに意味があるとお話がありました。おそらく白井さんの立場からすると勇気のいる決断だったと思います。白井さんのそうした思いに共感するとともに、自分でも「すごくやりたい」と思いました。
──ベースにあるのはプラトンの『饗宴』とのことですが、このテーマを選んだのは。

橋本:最初は、世田谷という土地柄からも文学的な下地の作品も面白いねという世間話。そこでプラトンの『饗宴』のことを思い出し、今の視点から疑問を投げかけ、そこに批判的な視点からツッコミを入れていきたいとお話しました。2024年の東京で『饗宴』が行われるとしたら、そこには誰がいるべきなのか、どんな愛が語られるのか、そもそも私たちが安全に愛を語れる場所は存在するのかを主軸に置いた作品になります。白井さんには最初は、ダンテの『神曲』というアイデアもあったんですよね。
白井:「ファウスト」を題材にした『デビルダンス』を観ていたこともあり、人間とはなにかというところで『神曲』を挙げたところ、橋本さんから『饗宴』が出てきて。その捉え方も含め、面白そうだと感じ即賛成しました。
橋本:この作品では、『饗宴』そのものをなぞるのではなく、むしろそれに対する批判、「今だったらこうじゃない?」というところをパフォーマンスで立ち上げます。個人として論じるというより、世界や社会の構造を作り、その中にいる個人の立ち位置(=境遇)における加害性、被害性の交差性を見せていきます。
※交差性(インターセクショナリティ)
差別を単独で考えるのではなく、セックス、ジェンダー、民族、年齢、社会経済的状況、セクシュアリティー、地理的位置、障害などさまざまな差別の軸が組み合わさり、相互に作用することで独特の抑圧が生じている状況
──具体的な創作の過程は。
橋本:まず稽古に入る前に、参加する一人ひとりと時間をかけて話をします。なにを求めてこの作品に飛び込んでくれたのか、なにをやりたいか、もしくはやりたくないかをヒアリングします。身体を動かす前に、まず人間としての信頼関係を築く意味でも必要な時間です。その人がどんなことを考えているのか、どのような幼少期を過ごしてきたのかなど、どういった話に発展するのかも人それぞれです。そこから読み取った情報をもとに、今回だったら7人のキャストが集まったときにどうなるのかを考えていきます。
次に7人の組み合わせ、関係性が見えてくると、それをもとにそれぞれの役割と展開を文字(文章)で組み立てていきます。演劇のプロットのようなものです。そうやってできたシーンに振付をしていく中で、実はこことここが繋がっていたのかと、導かれるようなこともたくさんあります。直感的にわかっていたことが、後で論理的な整合性をもつことは私の創作過程でよくあります。
──稽古で印象的だった出来事は。座組には多彩なキャストが揃っています。

橋本:(取材時)まだ全員そろっての稽古ではないのですが、今回のキャストの共通点は、指示されたことをうまくやることにやりがいを感じるタイプの人たちではなく、すでに自分の表現のプラットフォームを持っている人たちだということです。自分を使ってどんなことをするつもり?……と、良い意味で、私を試すようなところもあります。それがすごくいいなと思っていて。
私のプロットに対しても、キャストからツッコミが入ります。この意図を表現するのにこの方法が適切なのだろうかとか、人物像がぼやけているとか。確かにその通りで、私自身、人物によって解像度にムラがあるわけです。自分の経験に近しいキャラクターは解像度が高く、遠いところにいる人はぼんやりする。そうすると、「自分のキャラクターって“人A”みたいじゃない」って指摘してくれて(笑)、じゃあどうするかを考えていく。そういう指摘や意見から始まる対話がすごく豊かです。

橋本:印象的だったのは、今回、1シーンだけ台詞を使うのですが、その言葉を発するキャストとの創作過程で、その人自身が「自分は本当はこういうことを自分に言わざるを得ない状況にいたんだ」ということに気づく、人生観が変わってしまうくらいの瞬間がありました。それは私にとっても衝撃的なことで、だからこそ、そこに誠実に向き合い、最後まで責任をとる方法を考えなくてはならない。私にも大きな出来事でした。
また、これまでの創作と大きく異なるのは音楽です。これまでは既存の音楽をコラージュして創作してきましたので、オリジナルの音楽を用いるのはほぼ初めての経験となります。音楽担当の篠田ミルさんとは、5月中に演出、振付、音楽を一度、作っておこうと作業を進めていたので、実はすでに演出プランや動線も含めた振付はできています。その絵コンテがあればどなたでも上演できるくらいのレベルで仕上げました(笑)。

──既にそこまで!
橋本:それは稽古に全員がそろって変わっていくことを大前提としながらも、まずそれを提示したいからです。まだなにもありません、なんとなく作っていきましょうというのは、私にはちょっと無責任に感じるんです。
白井:「“とりあえずやってみましょう”はない」──『2020』のときも、そうだったことを思い出しました。ステージングの作業に入る前段階で、「ちょっと試してみますか」と言うと、「まだいいです」って。ずっと「まだいいです」なので、「まだいいの?」と思ったこともあったのですが、橋本さんは稽古場の後ろでずっと見ていて、白井がなにをやりたいのか、どんな空間なのかをすべて頭に叩き込み、その上で、しっかりとスケッチの中にどこでどうするか、カウントも含めてすべて落とし込んでいた。だから、いざ始めるとみるみるうちに形になっていったんです。僕からすると、橋本さんは万全の準備をする人。見習わなければいけないな(笑)。
橋本:クリエーションにはいろんなやり方があって、白井さんは違うタイプの方なので、そこは見習わなくても(笑)。
白井:僕もちゃんと準備はするんですよ(笑)。でもその場で一緒にトライ&エラーを繰り返していきながら決めていくってタイプなのでね。
橋本:私は、普段の様子を見ることで、その人の身体性がわかり、インスピレーションがわき、そこから的確なディレクションができる。いきなりリハーサルの場で動いてもらっても、普段やらない動きなので、その人の身体性に合っているのかよくわからないんです。

白井:ハラスメントに関しての問題を乗り越えなければ、この先、舞台芸術は存続しえないと思っています。現在のような構造になってしまったのはなぜなのかというところから、今一度、我々が考えていかなければならない。たとえば演出家は創作の場の権威者ではない。「音響」「照明」などと同じように、あくまでも「演出」という役割でしかない。決してヒエラルキーの頂点にいるわけではないということを理解するだけで、防げることがある。創作においては切磋琢磨し、ときに厳しい局面も起こりえます。でもそこに権力構造を作るのは無意味だということです。自分でも、その考えでやってきましたが、それでも経験上どこかに身に染みついているものもある。
以前に橋本さんから言われた「白井さんは権威ある立場にいる」という言葉にハッとさせられました。自分では権威があるという意識はなくとも、芸術監督とか演出家という立場にいるということを、まずはちゃんと自覚しなくてはいけない。橋本さんとの仕事や雑談からさまざまな気づきや学びがあります。

橋本:世田谷パブリックシアターは主催公演においてハラスメント防止講習を必須としています。それだけでもアーティストは安心して仕事ができます。内容も大事ですが、義務付けているということをメッセージとして発することがまず重要。ただ、正直、ハラスメントに関しては私のほうが見る目は厳しいと思います。年齢的にもハラスメントを受けやすく、実際受けてきた過去もあるので。これまで見過ごされてきたことをどこかのタイミングで変える、それが今だと思っています。
それと同時に、労働環境としての問題もあります。アーティストである前に、一労働者としての権利がないがしろにされがちな業界の体質も改善していく必要があると思います。コロナ禍を経てだいぶ解消されましたが、高熱があっても出演し続けることが美談として語られる誤ったプロフェッショナリズムは、人間を非人間化することなのではないか。アーティストを守るという視点から契約書を交わすタイミングも整えていきたい。
結局のところは人権の問題。この劇場に限らず、ジェンダーや国籍に対する理解、言葉の選び方を学んでいく必要があるということです。白井さんが、さきほど一瞬、私のことを「彼女」とおっしゃいましたが、私は「彼女」ではありません。そのようなミスジェンダリングは頻繁に起こっています。悪意のあるなしに関わらず、社会には本当にさまざまな人がいることに劇場の想定と対応が追いついていない。表現、創作の場として劇場に足を踏み入れた人たちが、そこで自分の存在を否定されるようなことを言われたり、扱いを受けたりという、あってはならないことが起きているのが実情です。
それをなくすために、私の現場でもスタッフの人たちに働きかけてはいますが、ハラスメント防止講習のように体系づけられたものではありませんし、あくまでも自助努力。今後、劇場が差別構造に対する理解を深めることは優先順位を上げて取り組むべきことだと思っています。それは劇場として、アーティストの育成、良い作品づくりのために絶対に必要なプロセスです。ハラスメントも労働環境もジェンダーへの理解、言葉遣いもすべて地続き、作品の内外どちらにも関わるものだと思っています。

白井:今の三人称のことに関しても、橋本さんははっきり指摘してくれるので気づくわけで、「その通りです、ごめん」と言えるんです。そうやって僕自身にも、悪意はなくともジェンダーに対する意識などは、しみついたものがある。劇場関係者としても、僕個人としても大変重要な問題提起をしてもらっています。
そして、橋本さんのこの考え方は創作方法や作品にも表れています。自分がやりたいことを一方的に押し付けるのではなく、キャストが表現するものの解像度を上げて見ようとして、もし解像度が悪ければ、なにが悪かったのかを考えて、もう一度見つめ直す。そうやって対話をしながら作られた作品は、一方的な力関係から生まれたものとは違う。これまでも、今回も、創作への姿勢が素晴らしい作品を生み出しています。だからこそ、ここで創作してもらうことで、私が願う世田谷パブリックシアターの将来的な姿を体現していただいているとも言えます。ここで生まれる『饗宴』を楽しみにしています。
橋本:ありがとうございます。
──最後に、観劇にあたってはプラトンの『饗宴』を予習した方がよいでしょうか。哲学と聞くとちょっと構えるところもあります。
橋本:『饗宴』を出発点にしていますが、ほぼ原形をとどめてないので読まなくいいと思います。結局、やっていることは「人間について」。哲学と線引きする必要もありません。
──肩の力を抜いてフラットな状態で劇場に足を運ぼうと思います。『饗宴』開幕を楽しみにしています。

終始穏やかに丁寧に考えを聞かせてくださった橋本さん。とても共感しました。白井さんが最初にお話をしてくださった『デビルダンス』をご覧になったときの共感はこのようなものなのかな。そんなことを感じました。白井晃芸術監督が、世田谷パブリックシアターが目指す道を象徴する『饗宴/SYMPOSION』は7月3日開幕です!


池貝峻 今村春陽 唐沢絵美里 Chikako Takemoto
田中真夏 野坂弘 湯浅永麻
稽古場写真提供:世田谷パブリックシアター
おけぴ取材班:chiaki(撮影・文)監修:おけぴ管理人

橋本ロマンスさん、白井晃さん
コロナ禍の社会に「ファウスト」「死の舞踏」のイメージを照らした『デビルダンス』
(21年)や、東京に生きる若者の焦燥感を映し出す『Pan』(21年、23年)など、革新的な視点で現代社会をとらえた作品を精力的に発表している橋本ロマンスさん。世田谷パブリックシアター芸術監督の白井晃さんとの対談が実現。
どのような作品なのかとともに、どのような人がどのような環境で、過程で創作しているのか。そのことの重要性にも気づかせてくれるお二人の話。『饗宴/SYMPOSION』がますます楽しみになります。
【『饗宴/SYMPOSION』までの道】

──まず、白井さんと橋本さんの出会い、そこから世田谷パブリックシアター主催公演として橋本ロマンスさんの新作『饗宴』上演を決定するまでのお話から伺っていきます。
白井:僕がKAAT神奈川芸術劇場の芸術監督をしていたときに『デビルダンス』を拝見し、作品から大きな衝撃を受けるとともに、橋本さんの舞台に対する意識、美学に共感を覚えました。そこで知り合いを通じてお話をする機会を設けていただきました。最初は仕事云々ではなく、お話しただけでしたが、ぜひお仕事でご一緒したいと思うようになり、僕が構成・演出をした高橋一生さんの一人芝居『2020(ニーゼロニーゼロ)』(パルコ・プロデュース2022)に参加していただきました。そして、世田谷パブリックシアターの芸術監督になり、僕自身が主体的にラインアップを決めるようになった最初の年度である2024年度に、プログラムのひとつを橋本さんに手掛けていただきたいと思いお声がけしました。
──ラインアップ説明会でも、白井さんがこれから打ち出していく方向性、劇場の在り方を象徴する演目だと感じました。それを受けて、橋本さんはどう感じましたか。
橋本:すぐに、「やります」と答えました。ただ、正直に言うと、お話をいただいたときは主劇場(世田谷パブリックシアター)だとは予想していませんでした。白井さんから、この劇場をフィジカルシアターなど様々な形態のパフォーマンスを上演する場所にしていきたいということ、若いアーティストの創作する場となってほしいという思いから、私が主劇場の演出を手掛けることに意味があるとお話がありました。おそらく白井さんの立場からすると勇気のいる決断だったと思います。白井さんのそうした思いに共感するとともに、自分でも「すごくやりたい」と思いました。
──ベースにあるのはプラトンの『饗宴』とのことですが、このテーマを選んだのは。

橋本:最初は、世田谷という土地柄からも文学的な下地の作品も面白いねという世間話。そこでプラトンの『饗宴』のことを思い出し、今の視点から疑問を投げかけ、そこに批判的な視点からツッコミを入れていきたいとお話しました。2024年の東京で『饗宴』が行われるとしたら、そこには誰がいるべきなのか、どんな愛が語られるのか、そもそも私たちが安全に愛を語れる場所は存在するのかを主軸に置いた作品になります。白井さんには最初は、ダンテの『神曲』というアイデアもあったんですよね。
白井:「ファウスト」を題材にした『デビルダンス』を観ていたこともあり、人間とはなにかというところで『神曲』を挙げたところ、橋本さんから『饗宴』が出てきて。その捉え方も含め、面白そうだと感じ即賛成しました。
【どんな作品?】
──特権性のある知識階級の男性たちが愛について論じていく対話編ということですが、それを身体表現などで舞台上にどう立ち上げていくのでしょうか。橋本:この作品では、『饗宴』そのものをなぞるのではなく、むしろそれに対する批判、「今だったらこうじゃない?」というところをパフォーマンスで立ち上げます。個人として論じるというより、世界や社会の構造を作り、その中にいる個人の立ち位置(=境遇)における加害性、被害性の交差性を見せていきます。
※交差性(インターセクショナリティ)
差別を単独で考えるのではなく、セックス、ジェンダー、民族、年齢、社会経済的状況、セクシュアリティー、地理的位置、障害などさまざまな差別の軸が組み合わさり、相互に作用することで独特の抑圧が生じている状況
──具体的な創作の過程は。
橋本:まず稽古に入る前に、参加する一人ひとりと時間をかけて話をします。なにを求めてこの作品に飛び込んでくれたのか、なにをやりたいか、もしくはやりたくないかをヒアリングします。身体を動かす前に、まず人間としての信頼関係を築く意味でも必要な時間です。その人がどんなことを考えているのか、どのような幼少期を過ごしてきたのかなど、どういった話に発展するのかも人それぞれです。そこから読み取った情報をもとに、今回だったら7人のキャストが集まったときにどうなるのかを考えていきます。
次に7人の組み合わせ、関係性が見えてくると、それをもとにそれぞれの役割と展開を文字(文章)で組み立てていきます。演劇のプロットのようなものです。そうやってできたシーンに振付をしていく中で、実はこことここが繋がっていたのかと、導かれるようなこともたくさんあります。直感的にわかっていたことが、後で論理的な整合性をもつことは私の創作過程でよくあります。
──稽古で印象的だった出来事は。座組には多彩なキャストが揃っています。

『饗宴/SYMPOSION』稽古場より
Ⓒ大洞博靖
私のプロットに対しても、キャストからツッコミが入ります。この意図を表現するのにこの方法が適切なのだろうかとか、人物像がぼやけているとか。確かにその通りで、私自身、人物によって解像度にムラがあるわけです。自分の経験に近しいキャラクターは解像度が高く、遠いところにいる人はぼんやりする。そうすると、「自分のキャラクターって“人A”みたいじゃない」って指摘してくれて(笑)、じゃあどうするかを考えていく。そういう指摘や意見から始まる対話がすごく豊かです。

『饗宴/SYMPOSION』稽古場より
Ⓒ大洞博靖
また、これまでの創作と大きく異なるのは音楽です。これまでは既存の音楽をコラージュして創作してきましたので、オリジナルの音楽を用いるのはほぼ初めての経験となります。音楽担当の篠田ミルさんとは、5月中に演出、振付、音楽を一度、作っておこうと作業を進めていたので、実はすでに演出プランや動線も含めた振付はできています。その絵コンテがあればどなたでも上演できるくらいのレベルで仕上げました(笑)。

篠田ミルさん『饗宴/SYMPOSION』稽古場より
Ⓒ大洞博靖
橋本:それは稽古に全員がそろって変わっていくことを大前提としながらも、まずそれを提示したいからです。まだなにもありません、なんとなく作っていきましょうというのは、私にはちょっと無責任に感じるんです。
白井:「“とりあえずやってみましょう”はない」──『2020』のときも、そうだったことを思い出しました。ステージングの作業に入る前段階で、「ちょっと試してみますか」と言うと、「まだいいです」って。ずっと「まだいいです」なので、「まだいいの?」と思ったこともあったのですが、橋本さんは稽古場の後ろでずっと見ていて、白井がなにをやりたいのか、どんな空間なのかをすべて頭に叩き込み、その上で、しっかりとスケッチの中にどこでどうするか、カウントも含めてすべて落とし込んでいた。だから、いざ始めるとみるみるうちに形になっていったんです。僕からすると、橋本さんは万全の準備をする人。見習わなければいけないな(笑)。
橋本:クリエーションにはいろんなやり方があって、白井さんは違うタイプの方なので、そこは見習わなくても(笑)。
白井:僕もちゃんと準備はするんですよ(笑)。でもその場で一緒にトライ&エラーを繰り返していきながら決めていくってタイプなのでね。
橋本:私は、普段の様子を見ることで、その人の身体性がわかり、インスピレーションがわき、そこから的確なディレクションができる。いきなりリハーサルの場で動いてもらっても、普段やらない動きなので、その人の身体性に合っているのかよくわからないんです。

【創作環境】
──公共劇場としての在り方。白井さんはなにを課題だと感じ、また橋本さんに期待することは。白井:ハラスメントに関しての問題を乗り越えなければ、この先、舞台芸術は存続しえないと思っています。現在のような構造になってしまったのはなぜなのかというところから、今一度、我々が考えていかなければならない。たとえば演出家は創作の場の権威者ではない。「音響」「照明」などと同じように、あくまでも「演出」という役割でしかない。決してヒエラルキーの頂点にいるわけではないということを理解するだけで、防げることがある。創作においては切磋琢磨し、ときに厳しい局面も起こりえます。でもそこに権力構造を作るのは無意味だということです。自分でも、その考えでやってきましたが、それでも経験上どこかに身に染みついているものもある。
以前に橋本さんから言われた「白井さんは権威ある立場にいる」という言葉にハッとさせられました。自分では権威があるという意識はなくとも、芸術監督とか演出家という立場にいるということを、まずはちゃんと自覚しなくてはいけない。橋本さんとの仕事や雑談からさまざまな気づきや学びがあります。

橋本:世田谷パブリックシアターは主催公演においてハラスメント防止講習を必須としています。それだけでもアーティストは安心して仕事ができます。内容も大事ですが、義務付けているということをメッセージとして発することがまず重要。ただ、正直、ハラスメントに関しては私のほうが見る目は厳しいと思います。年齢的にもハラスメントを受けやすく、実際受けてきた過去もあるので。これまで見過ごされてきたことをどこかのタイミングで変える、それが今だと思っています。
それと同時に、労働環境としての問題もあります。アーティストである前に、一労働者としての権利がないがしろにされがちな業界の体質も改善していく必要があると思います。コロナ禍を経てだいぶ解消されましたが、高熱があっても出演し続けることが美談として語られる誤ったプロフェッショナリズムは、人間を非人間化することなのではないか。アーティストを守るという視点から契約書を交わすタイミングも整えていきたい。
結局のところは人権の問題。この劇場に限らず、ジェンダーや国籍に対する理解、言葉の選び方を学んでいく必要があるということです。白井さんが、さきほど一瞬、私のことを「彼女」とおっしゃいましたが、私は「彼女」ではありません。そのようなミスジェンダリングは頻繁に起こっています。悪意のあるなしに関わらず、社会には本当にさまざまな人がいることに劇場の想定と対応が追いついていない。表現、創作の場として劇場に足を踏み入れた人たちが、そこで自分の存在を否定されるようなことを言われたり、扱いを受けたりという、あってはならないことが起きているのが実情です。
それをなくすために、私の現場でもスタッフの人たちに働きかけてはいますが、ハラスメント防止講習のように体系づけられたものではありませんし、あくまでも自助努力。今後、劇場が差別構造に対する理解を深めることは優先順位を上げて取り組むべきことだと思っています。それは劇場として、アーティストの育成、良い作品づくりのために絶対に必要なプロセスです。ハラスメントも労働環境もジェンダーへの理解、言葉遣いもすべて地続き、作品の内外どちらにも関わるものだと思っています。

白井:今の三人称のことに関しても、橋本さんははっきり指摘してくれるので気づくわけで、「その通りです、ごめん」と言えるんです。そうやって僕自身にも、悪意はなくともジェンダーに対する意識などは、しみついたものがある。劇場関係者としても、僕個人としても大変重要な問題提起をしてもらっています。
そして、橋本さんのこの考え方は創作方法や作品にも表れています。自分がやりたいことを一方的に押し付けるのではなく、キャストが表現するものの解像度を上げて見ようとして、もし解像度が悪ければ、なにが悪かったのかを考えて、もう一度見つめ直す。そうやって対話をしながら作られた作品は、一方的な力関係から生まれたものとは違う。これまでも、今回も、創作への姿勢が素晴らしい作品を生み出しています。だからこそ、ここで創作してもらうことで、私が願う世田谷パブリックシアターの将来的な姿を体現していただいているとも言えます。ここで生まれる『饗宴』を楽しみにしています。
橋本:ありがとうございます。
──最後に、観劇にあたってはプラトンの『饗宴』を予習した方がよいでしょうか。哲学と聞くとちょっと構えるところもあります。
橋本:『饗宴』を出発点にしていますが、ほぼ原形をとどめてないので読まなくいいと思います。結局、やっていることは「人間について」。哲学と線引きする必要もありません。
──肩の力を抜いてフラットな状態で劇場に足を運ぼうと思います。『饗宴』開幕を楽しみにしています。

終始穏やかに丁寧に考えを聞かせてくださった橋本さん。とても共感しました。白井さんが最初にお話をしてくださった『デビルダンス』をご覧になったときの共感はこのようなものなのかな。そんなことを感じました。白井晃芸術監督が、世田谷パブリックシアターが目指す道を象徴する『饗宴/SYMPOSION』は7月3日開幕です!


池貝峻 今村春陽 唐沢絵美里 Chikako Takemoto
田中真夏 野坂弘 湯浅永麻
【公演情報】
『饗宴/SYMPOSION』
2024年7月3日(水)~ 7月7日(日)@世田谷パブリックシアター
演出・振付:橋本ロマンス
音楽:篠田ミル
美術:牧野紗也子
照明:鳥海 咲
音響:遠藤瑶子
映像:山田晋平
舞台監督:川上大二郎、湯山千景
プロダクションマネージャー:木村光晴
出演:
池貝峻 今村春陽 唐沢絵美里 Chikako Takemoto 田中真夏 野坂弘 湯浅永麻
稽古場アンダースタディ:神田初音ファレル
公演HP
『饗宴/SYMPOSION』
2024年7月3日(水)~ 7月7日(日)@世田谷パブリックシアター
演出・振付:橋本ロマンス
音楽:篠田ミル
美術:牧野紗也子
照明:鳥海 咲
音響:遠藤瑶子
映像:山田晋平
舞台監督:川上大二郎、湯山千景
プロダクションマネージャー:木村光晴
出演:
池貝峻 今村春陽 唐沢絵美里 Chikako Takemoto 田中真夏 野坂弘 湯浅永麻
稽古場アンダースタディ:神田初音ファレル
公演HP
稽古場写真提供:世田谷パブリックシアター
おけぴ取材班:chiaki(撮影・文)監修:おけぴ管理人
ページトップへ