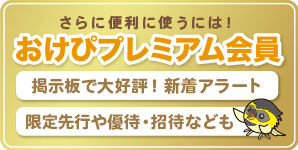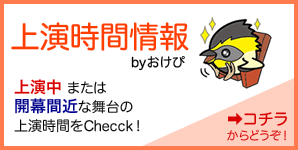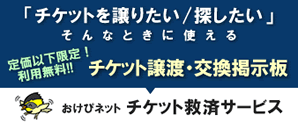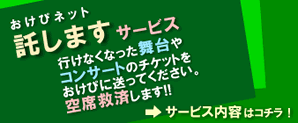- new おけぴ会員マイページができました
掲載日:2024/03/01
小川絵梨子×上村聡史×石川 慶(映画監督)登壇 新国立劇場『デカローグ1~10』スペシャルトークイベントレポート
『デカローグ』@新国立劇場小劇場
フルセット券や単券優待、レポ割枠などおけぴ会員限定チケット 申込受付中!
フルセット券や単券優待、レポ割枠などおけぴ会員限定チケット 申込受付中!
2024年4月~7月に上演される新国立劇場『デカローグ1~10』関連イベントとして、ポーランドの世界的映画監督 クシシュトフ・キェシロフスキが遺した傑作『デカローグ』の魅力を語るトークイベントが開催されました。

小川絵梨子芸術監督 石井 慶監督 上村聡史さん
登壇者は『デカローグ1~10』の演出を手掛ける新国立劇場 演劇芸術監督の小川絵梨子さん、上村聡史さん、スペシャルゲストは映画監督の石川 慶さんです。『デカローグ』を愛する3人のお話は深く濃く楽しい! 進行は編集者・ライターの大堀久美子さん。
『デカローグ」ご紹介
「トリコロール三部作」『ふたりのベロニカ』で知られる、ポーランドの名匠クシシュトフ・キェシロフスキが発表した 『デカローグ』。旧約聖書の十戒をモチーフに 1980 年代のポーランド、ワルシャワのとある団地に住む人々を描いた十篇の連作集です。人間を裁き断罪するのではなく、人間を不完全な存在として認め、その迷いや弱さを含めて向き合うことが描かれたこの作品は、人への根源的な肯定と愛の眼差しで溢れています。
【出会いはそれぞれ】
──『デカローグ』との出会いは? 石川監督は『デカローグ』を教科書のような映画とおっしゃっています。
石川監督)
まず簡単に自己紹介をさせてください。今では主に日本で映画を撮っていますが、僕はクシシュトフ・キェシロフスキが教鞭をとっていたポーランド国立映画大学で映画を学びました。僕が留学したときにはすでにキェシロフスキ監督は他界されていましたが、監督の“色”はしっかりと学校に残っていました。出会いについては、『デカローグ』は10篇ある中の5番目の「ある殺人に関する物語」と6番目の「ある愛に関する物語」の2篇は劇場公開されていたので見ていましたが全部は見ていませんでした。映画学校で、(撮る)題材を探すのに苦労していたときに教授から見るように勧められたのが『デカローグ』でした。そこで感銘を受け、それ以来、映画を作っていてなにかあると見返しています。それで教科書のような映画と言っています。

小川さん)
私はアメリカ留学中に知り合いから面白いよと勧められて見たのが出会いです。

上村さん)
大学時代、図書館で手当たり次第に洋画を見ていた中に『デカローグ』がありました。
当時はレーザーディスクだったのですが、「なにやら分厚いものがある! 10時間! 時間もあることだし見てみよう」という感じです。正直なところ、二十歳そこそこの僕には淡々とした世界観がちょっとよくわかりませんでした。それが! 今回のお話をいただいて見返したら、ここまでメタファーあり、人間の心理の機微の繊細な描写あり、こんなに深い作品だったことを知りました。ときが経過したことで気づくというのは映画ならではですね。
──『デカローグ』が多くの映画監督にとって特別な作品と言われる理由はどのあたりにあると感じていらっしゃいますか。
石川監督)
映画学校でも言われたことですが、『デカローグ』には映画のすべて、言い換えれば人間界のすべてが詰まっている。ワルシャワの小さな団地で起こる人間ドラマなのですが、そのミクロコスモスを通して、ストーリーやキャラクター、テーマという要素とともに、それよりもっと大きなものを扱っている。なんだか首根っこを掴まれて無理矢理に上から宇宙全体を見てみなさいと言われている感じがします。そこに「映画ってここまでできるんだ」と思わされる。映画作家だけでなく、舞台芸術に関わる人も含めたクリエイターの憧れ、ひとつの理想がそこにある気がしています。
──本作の舞台化は、小川さんがずっと温めていた企画なのでしょうか。
小川さん)
映画を見たときは「素晴らしい映像作品だ」と感じていたのですが、10年程経って「舞台でやりたい作品はありますか」と訊かれたときに浮かんだのが『デカローグ』でした。それまでにもワークショップで取り上げてはいましたが、舞台化を前提にしたものではありませんでした。でもやってみると「人間の物語として、ちょっと引いた大きな視点というところで演劇でもできなくないな」と思いました。ただ、ひとつずつ独立した話ですが、基本的には10篇で一つの神話、サーガになっているので、上演するなら10篇やりたい。それを上演するのはとても大変なことなので、ここ(新国立劇場)でやることにしました(笑)。
──石川監督は、舞台化されると知ったときにどう思われましたか。
石川監督)
正直なところ、仲間に入れて欲しかったなと思いました(笑)。そして全10篇を上演すると聞き、また出演する俳優の顔ぶれを見て「ガチなやつだ!!」と、ワクワクしています。
──上村さんには演出のオファーを受けたときの気持ちをお伺いします。
上村さん)
二つ返事で引き受けました。機会があって、ポーランドのワルシャワへ行くことがあり、以来、年に一度はポーランドを訪問していた時期もあるくらい好きな土地です。また、演出の立ち上がり方がとても繊細で、常に地獄の葛藤、生きる葛藤を新しい手法で立ち上げる演劇に挑戦するクリスティアン・ルパとクシシュトフ・ヴァルリコフスキという2人の演出家から影響を受けました。彼らがけん引するポーランド演劇界というのは、俳優の表現も無駄なものをそぎ落としエッジが効いている。そして人や建物に奥行きや個性を感じるワルシャワの町の景色にも惹かれ、そこに繋がるこの作品のオファーが来たときは即、お引き受けしました。舞台化に対しては、映像でここまで評価の高い作品ですから、舞台芸術ならではのやり方というところに苦労するだろうと思いながら、一方で「この人物関係や台詞ならば舞台でもいける」と思いました。
──二人の演出家が交互に演出を手掛ける本公演。世代の近い演出家同士で互いの手の内を明かす(⁉)ことへは。

上村さん)
僕としては通常はちょっと考えられないことなのですが(笑)、長いお付き合いの中で小川さんはフレキシブルな思考をお持ちの方だと認識しています。僕らは演出のプロセスの踏み方は違うのですが、大事にしていることが似ている。俳優の中にあるものが物語になる、だからその瞬間、その瞬間の芝居をちゃんと積み上げていくという信念にシンパシーを感じているので、小川さんとならできると思いました。
小川さん)
劇場としてもフルオーディション企画にも複数回関わっていただくなど上村さんと信頼関係を築いてきました。また個人的にも、上村さんとは“頼りにする役者さん”が結構同じで、こういう言い方が適当かわからないのですが“似たようなところに生息している”気がしています(笑)。ちょっと偉そうな言い方になってしまいますが、上村さんを信じてお任せします。
【劇場で味わう『デカローグ』】
──演劇でしかできない『デカローグ』とは。小川さん)
旧約聖書の「十戒」は宗教というだけではなく人間の根源的なもの、社会生活の中で人が流されてしまうことが戒めとして記されているように思います。そして『デカローグ』は厳しさの中にも人間が悩み、不安になり、後悔する、自分をごまかすなど人間の弱さに寄り添う“人間の存在への肯定感”という視点で、そこにある感情を楽しい、悲しい、怒りなどの単色カラーではなくグラデーションで描く作品。舞台では、その複雑で生々しい感情―自らの中での、社会の中での、相手との間での言葉にならない葛藤―を、体温を感じながら味わっていただけるのではないかと思っています。それを目指して頑張ります。
上村さん)
舞台芸術ならではとなると、たとえば本当の手紙と嘘の手紙、手紙がキーワードになる話があるのですが、映像ではクローズアップで伝えられるところが、舞台では難しい。そこである仕掛けを使って、それを可視化しようと思っています。ほかにも、ある話では“覗き”(視点)がポイント、前半と後半の視点の移行の面白さがあります。映画では2つの視点になっていましたが、実は元の脚本にはあったもうひとつの視点を復活させ3つ目の視点に移行させてみるなどの作業をしています。そうやって、生きていくことの生々しさ、そこに大きくのしかかる葛藤を舞台芸術で効果的に届けたいと思っています。
【全部好き!】
──10篇の中で好きなエピソードは。石川監督)
やっぱり第1話かな。独特のエンディングがね。行き詰まりの中でもキェシロフスキの冷たさと温かさが同時に感じられる。だから第1話なのかなって。
小川さん)
第1話を演出するのは私ですが、ハードルがどんどん上がっています(笑)。実は個人的には第1話が一番難しいと感じています。

石川監督)
ちょっと「トリコロール」のような感じもあり、すごく大事な話だと思います。
小川さん)
(プレッシャーを感じつつ)あの……もう一つ選ぶとしたら?
石川監督)
もう一つ選ぶとしたら、全然違う第10話。最後に希望で終わるっていうのがすごくいいなって。ある種、落語的な感じもあり、全然難しくないというのがすごく好きです。でも下手するとちょっと浮いてしまうので、この世界観の中にどう馴染ませるか興味があります。つまり、1と10が好きってことは、その間も全部好きということです(笑)。

第10話の演出は……小川さん
上村さん)
僕が好きなのは第8話の「ある過去に関する物語」。倫理学の教授とユダヤ人の民族学の研究者、二人の女性の話なのですが、二人の距離感はもちろん、過去との距離感も含めて興味があって、この話は僕に演出をさせてくださいと申し出ました。第7話も好きで、そう思うと僕はキェシロフスキの女性の描き方が好きなのかな。カッコイイと言ってしまっては言葉が簡易的過ぎるのですが、多面的でありながら独特の美学があるように思います。
あと、ちょっと質問から離れますが、第1話から第10話、真冬から始まり最後に夏に向かうというのも面白いなと思いました。
小川さん)
私は一番有名な第5話、第6話が好きです。第10話もすごく楽しく好きです。ただ、今は第1話の稽古スタートを前にちょっと怖いなと感じています、自らが企画したにもかかわらず(笑)。『デカローグ』の世界観を立ち上げる! とにかく正直に作らなくてはいけないと思っています。映画の世界をただ表層的に真似しても、そこに嘘があるとお客様には絶対に見抜かれる。ただただ正直に作っていこうと思います。
イベントはこの小川芸術監督の力強い言葉で終了。石川監督からも「全10篇を上演するというのは歴史的な大仕事」との言葉もあったように、4月から7月まで続く『デカローグ』は紛れもなく壮大な企画です。ただ、1篇ずつは1時間ほどの作品で
デカローグ1~4[プログラムA、B交互上演]
2024年4月13日[土]~5月6日[月・休]
デカローグ5・6[プログラムC]
2024年5月18日[土]~6月2日[日]
デカローグ7~10[プログラムD、E交互上演]
2024年6月22日[土]~7月15日[月・祝]
という3つの期間に分かれての上演となりますので、ご予定の調整は必要ですが、体力的な“観るハードル”は意外に低いのかなとも思います。そして「よーし!10篇見るぞ!」という方にはお得なセット券もございますよ。
各話に「ある〇〇に関する物語」というタイトルがあり、〇〇には順不同で「告白」、「運命」、「孤独」、「愛」、「過去」、「クリスマス・イヴ」、「選択」、「父と娘」、「希望」、「殺人」といった言葉が入ります。この言葉たちを眺めているだけでも、どんな話が始まるのか楽しみになってきます。まずは4月13日より始まるデカローグ1~4のプログラムA・Bの交互上演で、『デカローグ』の世界を味わってみましょう。
『デカローグ』@新国立劇場小劇場
フルセット券や単券優待、レポ割枠などおけぴ会員限定チケット 申込受付中!
フルセット券や単券優待、レポ割枠などおけぴ会員限定チケット 申込受付中!
【公演情報】
『デカローグ 1~10』@新国立劇場 小劇場
公演日程2024年4月13日(土)~7月15日(月・祝)
デカローグ1~4(プログラムA&B 交互上演):2024年4月13日(土)~5月6日(月・休)
デカローグ5~6(プログラムC):2024年5月18日(土)~6月2日(日)
デカローグ7~10(プログラムD&E 交互上演):2024年6月22日(土)~7月15日(月・祝)
【原作】クシシュトフ・キェシロフスキ/クシシュトフ・ピェシェヴィチ
【翻訳】久山宏一 【上演台本】須貝 英 【演出】小川絵梨子/上村聡史
公式HP:https://www.nntt.jac.go.jp/play/dekalog/
『デカローグ 1~10』@新国立劇場 小劇場
公演日程2024年4月13日(土)~7月15日(月・祝)
デカローグ1~4(プログラムA&B 交互上演):2024年4月13日(土)~5月6日(月・休)
デカローグ5~6(プログラムC):2024年5月18日(土)~6月2日(日)
デカローグ7~10(プログラムD&E 交互上演):2024年6月22日(土)~7月15日(月・祝)
【原作】クシシュトフ・キェシロフスキ/クシシュトフ・ピェシェヴィチ
【翻訳】久山宏一 【上演台本】須貝 英 【演出】小川絵梨子/上村聡史
公式HP:https://www.nntt.jac.go.jp/play/dekalog/
おけぴ取材班:chiaki(撮影・文)監修:おけぴ管理人
ページトップへ