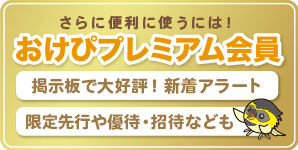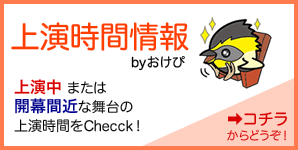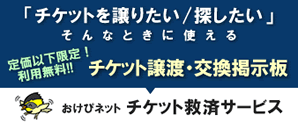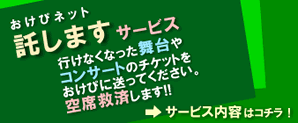- new おけぴ会員マイページができました
掲載日:2024/03/27
ミュージカル『VIOLET』演出:藤田俊太郎さんインタビュー
2024年4月7日に東京芸術劇場プレイハウスにて開幕するミュージカル『VIOLET』。演出を手掛けるのは、先ごろ第31回読売演劇大賞を受賞されたことでより一層演劇界の注目を集める藤田俊太郎さんです。「英国キャスト版」(2019年)、「日本キャスト版」(2020年)に続いて挑む2024年のミュージカル『VIOLET』について、制作発表会見後にお話を伺いました。

藤田俊太郎さん
──まずは読売演劇大賞、最優秀演出家賞受賞そして、大賞おめでとうございます。
ありがとうございます。これからもいい仕事をしていくことでしか恩返しはできないと思っています。とにかく感謝しかありません。
──ご自身の中で何か変化は。
自分を突き動かし続けるのは「いい芝居を創りたい」という想いだけだと、明確になりました。演劇を創ること、ミュージカルを創ること、演出の仕事は本当に面白いと改めて思っています。今は『VIOLET』に全力で取り組みたい。その気持ちだけです。

──多彩なキャストとともに、ここから『VIOLET』をどのように創っていかれるのでしょうか。
この話のベースには「オズの魔法使い」があります。ドロシーの旅になぞらえて、ヴァイオレットは傷を癒してもらうためにテレビ伝道師に会いに行く。たどり着いたときに現れるのが伝道師だけではなく、自分の過去とも向き合うことになるという話です。この作品を読み解いていくには、ヴァイオレットが、旅の過程で出会う登場人物たちとどのように「鏡」になっていくかが大切になります。「鏡」というのは、自分自身をどう見ているのかでもあり、自分がどう見られているのかでもある。その2つの繰り返しの先に、最後、どんな出会いがあるのか。まずは台本に描かれた道筋をしっかりと組み立てていくことが重要だと考えています。
そこにもう一つ、時代背景も大きく関わってきます。これは1964年の話です。揺れ動くアメリカ、世界全体を見回しても常に情勢は変化し続けています。人々がどのような政権下で、何を感じ、何と闘っているのか。2024年に、今一度アメリカの60年代を再定義するためには、何が必要なのか。女性の視点、ほかにもいろんなことが交錯してくるでしょう。演出をする上では「いつこの作品を上演するか」という切り口も大きく影響します。
──観客は2024年の日本にいながら60年代アメリカを見るような、逆に60年代アメリカに身を置きながら今を感じるような。客席はどちらの世界になるのかなということをふと思いました。
両方だと思います。それを雄弁に物語るのが、非常に優れた本作の音楽です。60年代、もしくはアメリカにおける様々なルーツ音楽のようでありながら、現代的な音階も入ってきます。60年代の音楽をどのように再構築すると、現代を生きる僕たちが当時の空気を感じられるのかを具現化している音楽です。これはリバイバルの根本にある考えですよね。観客の皆様は視点を1964年のアメリカに置きつつ、今の世界、自分自身の生活、人生を追体験することもできる。非常に豊かな作品だと思います。

──先ほどから藤田さんのお話が「なるほど」過ぎて、もはや「なるほど」しか言葉が出てきません。と言いつつ、次の質問を。ヴァイオレットは顔に大きな傷を負っていますが、舞台上のヴァイオレット役の俳優にメイクアップで傷を描くことはしません。そこに至った経緯は。
台本には音楽のジニーン・テソーリさん 、脚本・歌詞のブライアン・クロウリーさんの思いとして「傷をメイクアップで表現すべきではないかもしれない」と記しています。指示というよりあくまでも注意書き。どうするかは演出家に委ねられているのですが、メイクアップで傷をつけるという選択肢は、今の僕には100%ありませんでした。それは目に見える傷というものが、この作品にとって必要な要素ではないと思うからです。
必要なのは、いかに傷を想像させるか。心の傷のメタファーにも、自分が人を傷つけたことのメタファーにもなりうる。自分だけの傷ではないのです。だからみんなが鏡になり続けるということは、その分だけ傷が存在するということ。そこから考えられるのは、誰しもが人を傷つけるかもしれないし、傷つけられるかもしれない。永遠に消えることのない傷だって心の中にはあるのかもしれない。様々なメタファーだと考えると、メイクアップで見せることよりも想像させることこそが大事だと、演出家として再認識させられているところです。
──キャストとはどの程度認識を共有されているのでしょうか。
そこは頬のこちら側のこの場所にこういう縫い跡があってというような細かいところまで共有しています。それはアジア人、日本人として生活している私たちが黒人役をどう解釈するのか、白人役をどう解釈するのか、それと同じこと。違う人種をどう演じるのか、傷がある人物をどう演じるのか、キャラクターのバックグラウンドの情報のひとつとして考えればほかの役作りと大きく違わないのではないでしょうか。やはり演劇の面白さの根本は想像力にあると思っています。

──この作品は他者との出会い、相関の物語でもあるように思います。相手を「見る」とか「聞く」という言葉がたくさん出てきますが、見るという行為とイマジネーションの結びつきについてはどのように感じていらっしゃいますか。
そこは原文、英語では明確に書かれていて、たとえばヴァイオレットとフリックで「私を見るとき何が見える」「俺を見るときに見えるもの?」というやりとりが何度も繰り返されるのですが、この「見る」が英語では「look at」と「see」なんです。すごくシンプルな話で、私があなたをlook atするとき何がseeできるのかということ。つまり表面的に「見る」ということの向こう側に、もうひとつの「見る」、共鳴するとか共感するなどがあり、それがイマジネーション、想像力と呼ばれるものなのではないか。そう考えると、『VIOLET』は彼女が鏡である人たちとどうseeしてきたのかという話だとも言えます。それをお客様はずっとlook atしていただけなのか、それともseeしていたのか──という物語の構成になっているんです。そのことは翻訳にも反映していただいていますが、「look at」と「see」について僕自身がカンパニーの皆に明確に伝えられるようになったことで、新たな作品世界が少しずつ具現化できています。それが2024年バージョンで生まれるもののひとつに繋がるのではないでしょうか。
──続いて、伝道師の存在について伺います。今、私たちが見ると「騙されている」と感じますが、ヴァイオレットにとっての伝道師はそうではない。
物語の舞台となるのは1964年。テレビ、冷蔵庫、車、持ち家……アメリカが豊かになっていく一方で、冷戦下、常にソビエトという大国の存在がそこにある。そんな時代です。顔の傷を治す方法は医療でもなく、祈りでもなく、テレビの中でいろんな傷を癒している伝道師。テレビの映像を見て、ほかに方法がなくなれば伝道師を信じるヴァイオレットの気持ちにはとても共感できます。もちろん今だったら、整形医療などで傷を消すことはできるかもしれませんが、それは選択肢が増えたというだけで、何かを選択し、それを信じる気持ちは普遍的なものだと思っています。共感というところでは、ヴァイオレットが特別な誰かではなく私たちと同じ一般市民であるということも大切な要素です。
──本作においてはヤング・ヴァイオレットが担う役割も大きなものがあると思います。
とても重要な存在です。ヴァイオレットが、傷を負った瞬間や父親に向き合うためには、彼女は自分の過去とも向き合わなくてはならない。この物語は、ヴァイオレットの旅であると同時に、ヤング・ヴァイオレットがいずれなるヴァイオレットに向かって旅するという二重構造になっており、実は作品の幕開けから、そのことが観客にしっかりと受け渡されているんですよ。
また、ヤング・ヴァイオレットの存在から感じることは、この作品には完成と未完成が混在しているという魅力があるということです。音楽の高い完成度とそこで描かれるヴァイオレットの内面の揺らぎ-自分なりの価値観をまだ見つけられていないアメリカ南部の少女が傷を負うこと、傷を治そうとすることでどう変わっていくのか-その道筋が一本道でないという対比。旅の起点ともう言うべきもう一人のキーパーソンはいずれ傷を負う、もしくは傷を負った瞬間を担うヤング・ヴァイオレットなのです。そして二人が交錯し、価値観の変化していく旅を読み解き、自分自身にも問うていくと、やがて誰もがヴァイオレットなのだと思えてくるのです。それが作家、音楽家がこの作品に託したことなのかもしれません。これからも自分に問い続けていきたいです。

──では最後に2018年のアメリカ南部の旅、2019年のロンドン公演、2020年の日本公演と藤田さんも『VIOLET』と旅をしてきました。ここまでの旅でご自身の中に残ったものは。
全部と言ったら大げさに聞こえるかもしれませんが、アメリカを横断したことも、演出家としてロンドンまで連れていっていただいたことも、2019年、2020年のカンパニーで一緒に創作できたことも、体験としてあまりにも大きすぎて、正直、自分の中で何が起きているのかまだわからないです。得られたものが多すぎて。ただ、はっきりと言えることはどの旅も素晴らしい旅だったということです。そして、今また次の目的地を目指す新たな旅がスタートしました。僕はこの作品を奇跡の物語だと紹介していますが、僕にとっても『VIOLET』は奇跡のような現在進行形の旅です。チャリングクロス劇場でご一緒したみなさんも、2020年のカンパニーのみなさんも人間として尊敬できる大切な仲間です。僕はみなさんから与えてもらうばかりで、何かを渡すことができたのだろうかと考えると、やっぱりもらってばかりだったと思うんです。だから彼らに恥ずかしくない仕事をする、次の『VIOLET』をいい公演にすることで、少しずつでも恩返ししていきたいと思っています。
──会見でのコメントも十人十色、多彩な顔ぶれのキャストと立ち上げる2024年の『VIOLET』も楽しみにしています。
今回のキャストのみなさんからも稽古場でたくさんの気づきをもらっています。それぞれがもつ価値観の違いはもとより、俳優としての出自や芝居を作る方法論が違う人たちが集まって、他者を受け入れ合いながら作品を作る。とても有機的なクリエーションができています。ぜひ劇場で2024年の『VIOLET』を一緒に旅しましょう。お待ちしています。
STORY
1964年、アメリカ南部の片田舎。
幼い頃、父親による不慮の事故で顔に大きな傷を負ったヴァイオレットは、
25歳の今まで人目を避けて暮らしていた。
しかし今日、彼女は決意の表情でバス停にいる。
あらゆる傷を癒す奇跡のテレビ伝道師に会う為、西へ1500キロ、人生初の旅に出るのだ。
長距離バスに揺られながら、ヴァイオレットは様々な人と多様な価値観に出会い、
少しずつ変化していく。長い旅の先に彼女が辿り着いたのは―。
【公演情報】
ミュージカル『VIOLET』
<東京公演>
2024年4月7日(日)~4月21日(日)/東京芸術劇場プレイハウス
<大阪公演>
2024年4月27日(土)~4月29日(月・祝)/梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
<福岡公演>
2024年5月4日(土・祝)/キャナルシティ劇場
<宮城公演>
2024年5月10日(金)~5月11日(土)/仙台電力ホール
音楽:ジニーン・テソーリ
脚本・歌詞:ブライアン・クロウリー
原作:ドリス・ベッツ『The Ugliest Pilgrim』
演出:藤田俊太郎
出演:三浦透子/屋比久知奈(Wキャスト) 東啓介 立石俊樹
sara 若林星弥 森山大輔 谷口ゆうな 樹里咲穂 原田優一 spi
生田志守葉 嘉村咲良 水谷優月(トリプルキャスト)
木暮真一郎(スウィング) 伊宮理恵(スウィング)
ミュージカル『VIOLET』公式HP
ミュージカル『VIOLET』
<東京公演>
2024年4月7日(日)~4月21日(日)/東京芸術劇場プレイハウス
<大阪公演>
2024年4月27日(土)~4月29日(月・祝)/梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
<福岡公演>
2024年5月4日(土・祝)/キャナルシティ劇場
<宮城公演>
2024年5月10日(金)~5月11日(土)/仙台電力ホール
音楽:ジニーン・テソーリ
脚本・歌詞:ブライアン・クロウリー
原作:ドリス・ベッツ『The Ugliest Pilgrim』
演出:藤田俊太郎
出演:三浦透子/屋比久知奈(Wキャスト) 東啓介 立石俊樹
sara 若林星弥 森山大輔 谷口ゆうな 樹里咲穂 原田優一 spi
生田志守葉 嘉村咲良 水谷優月(トリプルキャスト)
木暮真一郎(スウィング) 伊宮理恵(スウィング)
ミュージカル『VIOLET』公式HP
おけぴ取材班:chiaki(撮影・文)監修:おけぴ管理人
ページトップへ